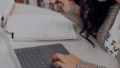建築現場では、天候との戦いがつきもの。特に木造住宅の施工中、突然の雨に見舞われることも少なくありません。そんなとき、現場で必ず問われるのが「この濡れた構造材、使っても大丈夫なのか?」という問題です。
この記事では、施工管理職としての経験をもとに、雨に濡れた木材のリスクと判断基準について解説します。
木造建築は雨に濡れても すぐに問題が発生するわけではありません が、長期間濡れたままだと カビや腐食の原因 になる可能性があります。
一般的に、木材は 含水率20%以下 に乾燥させた状態で使用されるため、短期間の雨なら問題は少ないですが、連日の強い雨 にさらされると影響が出ることがあります。
雨に濡らさない対策と濡れた場合の注意点
ひとえに濡れる、と言っても様々な状況があります。
すでに組みあがった柱や梁
これから組み上げる予定で寝かせてある木材。
床の剛床・屋根の野地板など。
いずれも共通して言えるのは、長期間濡れたままの放置は問題ありますが、乾燥させれば問題ありません。
しかし、濡れた状態で次の工程に行くのは問題があります。
・濡れた柱、梁に外部の防水紙の施工:水分を閉じ込めてしまいます。
・濡れた剛床にフローリングなどの仕上げ作業:フローリングのそりやカビの原因に
剛床の養生として、大きいサランラップのようなシートを敷くこともあります。
大型サランラップ(粘着養生シート)は雨のリスクを抑えるために丁寧な施工かと思いますが完全には防水できないので、もしシートの下に雨が入ってしまった場合は、早めにはがして乾燥させた方がよいです。もちろん、はがす頃には屋根のルーフィングが貼れていることが前提になります。外周部が透湿防水シートで囲まれればなお安心です。
また屋根に石こうボードを敷く場合は、基本的に雨模様な時は施工を中断しましょう。ルーフィング材を敷くまでの間に雨が降りそうな場合は中断せざるを得ません。(上棟の時など)
国宝・重要文化材などは全体を覆う
下の写真は奈良県の興福寺 五重塔の工事用の囲いです。

全体を覆うことで雨・風を防いでいます。天候に左右されず、また木部などを濡らすことはありません。
しかし、通常の工事でここまでの仮設を準備するのは困難です。
困難というより国宝以外でこのような囲いは見たことはありません。
費用面はもちろん、仮設を立てるための周囲の広さのゆとりも必要です。
屋根を設けるとレッカーによる楊重作業も困難なため、レッカーの駐車スペースまで含めて仮設の計画をする必要もあります。
構造材を濡らしてほしくない。気持ちはわかります。しかし、
雨なんていつ降るかコントロールできません。また、常に進捗し形を変える工事現場でいつでも完全に雨養生するのは困難です。もちろん、ブルーシートなどの養生は必要ですし、
上棟日を雨の日を避ける、剛床に粘着養生シートを使用する、などの対策は必要です。それでも濡れてしまった場合、現場監督の本音としては、濡れ日しまう原因をすべて現場の責任にされてもどうしようもありません。濡らしたくないのであれば、国宝ような囲いが必要です。その計画がない、資金がない、敷地の余裕がないのであれば、責任は現場管理だけでないかと思います。過剰に心配せずに、乾燥させて次工程に進めればよいかと思います。
雨に打たれた木材は、すぐに“使えない”と決めつけるのは早計です。含水率、乾燥方法、変形の兆候——正しく見極めることで、現場は無駄なく、安全に、そして美しく仕上がります。現場監督としての経験から、これからも“判断の軸”を届けていきます
下記は別の参考ブログになります。